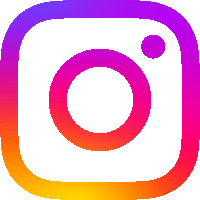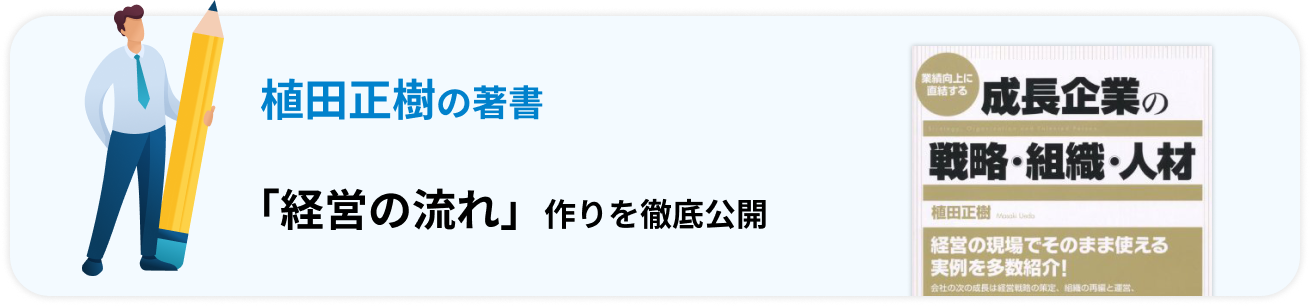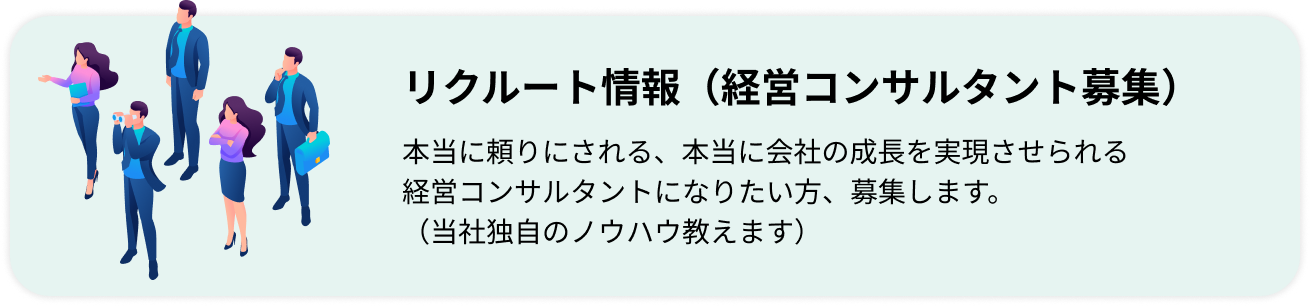-
01
自社の経営計画は、もっぱら予算数値と部署別の課題等で構成されている
-
01解説
全社の視点で「経営戦略」が策定され、かつ社内に浸透していますか?
全社のビジョン、基本的な戦略・課題あっての部署課題であることを再確認することでさらなる発展が期待できます。経営の現場では、中期的な全社のビジョンや基本戦略がはっきりしないままに短期的な数値のオンパレード(数値をきれいに羅列させているだけ、具体的な前提や根拠の全くない数値)となっている経営計画書をよく見かけます。 また、部門の課題や活動が、優先度や重要度等の整理なく箇条書き・網羅的に記載してあり、どこからどのように手を付けていいかわからないようなものも少なくありません。ビジョンや経営戦略とセットでの数値、全社の基本的な戦略・課題あっての部署課題、個人目標であることを認識した上で、実行力を担保できる経営戦略・計画を作成することをお勧めします。
Company diagnosis会社診断

会社診断
あなたの会社にあてはまるものはありますか?以下の10項目について確認して下さい。
-
02
自社には他社と価格競争を行う必要のない独自の商品(サービス)等はない
-
02解説
独自の商品(サービス)を作り上げるために必要なのは、それらの取り組みを戦略策定の中に織り込んでいくことです。今後の存続・成長を左右する重要なテーマとなるでしょう。
「売れないので価格を下げる」「競合他社との競争に勝つために低価格で勝負する」といった消耗戦略は、特に中小・中堅企業にとっては、疲弊・衰退を招いていくことになりかねません。 業種を問わず、他社にない、他社と価格以外の要素で差別化できる自社にしかない商品・サービスを見いだしていくこと、提供していくことが、今後は、今まで以上にとても重要になります。 こうした取り組みを、会社の戦略策定の中にしっかりと織り込み検討・策定していくことが必要です。
-
03
市場や顧客ニーズへの対応が会社としてうまくいっているとはいえない
-
03解説
市場・顧客ニーズへの対応は、営業部門内の取組にとらわれることなくマーケティングや組織・人財面にも絡んだ経営的視点から解決すべき問題です。
大局的視点を持って、改めて検討してみる必要があります。③は、「マーケティング的問題」と「組織・人財の問題」を併せ持つ項目です。 顧客ニーズへの対応や顧客ニーズを先取りした対応を行うためには、営業部門はもとより営業以外の部門(例えば、仕入、設計、製造、企画、管理等)も部署としての役割(機能)を明確にした上で、相互に協力した対応を行っていくことが必要です。企業規模の大小に関わらず、中小企業であっても、売れる仕組みを企画・コントロールする営業企画部署やマーケティング部門・部署や担当をあえて設置することで、全社的観点を持つことにつながったり、顧客志向のマーケティング対応を行う出発点となることも認識しておく必要があります。
-
04
部門(部署)間の仲が悪い。互いの主張がぶつかり解決しない。うまく連携できない
-
04解説
見つめるべき先は「顧客」です。社内の関係者を「顧客」と捉え、社外の顧客(得意先等)に全社の視点で自社の商品等の価値を提供する視点を持ち、かつ、社内で連携することを価値とするような組織目標や評価基準を作成できているか、改めて検討することが必要でしょう。
例えば、製造業の経営の現場では、「営業と製造(設計)は仲が悪い」といった話をよく聞きます。 営業は、「受注をとってきたのだから製造は高品質で早く作れ」といい、製造は、「こんな安値、短納期で受注してきて何考えているんだ」等と、売れない理由を他部門のせいにしてしまうようなケースです。 こうした場合、両者の先にいる「外部顧客(得意先等)」へ、会社全体として価値提供を行っていく視点が忘れ去られています。 必要なのは、「全社の視点」です。 と同時に、社内の各部門が協力して業務運営を行うことを価値とするような「組織目標」や「評価基準」を設定・運用することも重要な要素となるでしょう。
-
05
社内に噂や口コミが多く、不確定な情報が一人歩きすることが多い
-
05解説
公式な意思決定を公表するルートが社内に十分に整備されていない可能性も・・・
経営戦略の明確化とあわせ、実行のための組織構造について検討してみましょう。⑤に該当する会社は、組織体制・構造が曖昧であることと併せて、意思決定ルートが混乱していたりコミュニケーションの弱い会社であることが多いです。 迅速・正確・タイムリーに伝わらないといけない情報が円滑に伝わらないために、非公式の噂や口コミ等が、伝わらないこと、わからないことへの「フラストレーション」や「不安」を代弁する形として現れるのが一般的です。 対処法としては、まず、会社の経営戦略の明確化、実行のための組織体制の整備、組織運営の革新を行っていくことをお勧めします。
-
06
顧客からのクレームが多い。自社のクレーム対応の方法、レベルには問題がある
-
06解説
クレーム対応を統率・牽引できる責任部署はありますか?
その場しのぎ的な対応ではなく、顧客ニーズを吸収する貴重な情報源ととらえ、組織的に取り組む必要があります。クレームの問題の根っこには「組織の問題」が潜んでいることをまずは確認しておきましょう。クレームが適切に処理されれば、クレーム顧客は、リピート顧客になる確率が高いと言われています。しかし、クレーム対応のとりまとめ的責任部署が存在せず、クレームを社内でたらい回しにしたり、その場しのぎの対応をすれば、顧客は永久に会社から去っていってしまいます。そして、肝心のクレームは減るどころか増えていってしまうでしょう。 責任部署の明確化とともに、こうした情報を貴重な顧客のニーズとして受け止める組織的取り組みが不可欠です。
-
07
営業部門の評価基準は売上や利益等の数値で定量的に捉えている一方、
営業以外の業務部門や管理部門の評価軸は曖昧である -
07解説
部門ごとの役割に応じた定量的な業績評価軸を作成する等、組織の仕組みとして整備・改善することが必要です。
営業部門の評価は、「売上」「粗利益」「新規開拓件数」程度にとどまり、短期・結果志向の評価軸となってしまっている会社も少なくありません。一方で、定量(数値)化しにくい管理・間接部門(総務・経理・仕入・品質管理・製造等)や所属員の評価軸は、定量化できないと思われ、曖昧なものとなっている会社も多くあります。管理・間接部門の評価軸を定量化することはもちろん可能ですし重要です。営業部門も含めて、評価軸を多面的な視点を持って定量化するとともに、部門ごとの役割に応じた業績評価軸の設定や、各個人の成果・能力についての評価の仕組みも併せて整備していくことが必要となります。
-
08
若手が管理職になりたがらない。管理職といっても事実上プレーヤーである
-
08解説
世代間格差や価値観の相違と受け取らず、若手社員を適正に評価・育成し、魅力ある管理者像を示すためにも、自社の将来像や戦略を明確にし、それに沿った人事制度について、改めて見直してみましょう。
「若手が管理職になりたがらない」という話を聞いたとき、「世代の格差や価値観の多様化」等という言葉で片付けてはいけません。まず、「原因は社内にあり!」と考えるべきです。若手社員が成長し、いずれ管理者になったときにどんな役割や仕事が待っているか、責任ある魅力ある管理者像を具体的に示せない会社では、こうした発言が相次ぐケースも少なくありません。若手社員に、会社の将来像を「戦略」として明確に示すことを起点として、「実行の主体である人財に関わる仕組み」=「人事制度」を改めて見直してみることから、始めてみることをお勧めします。
-
09
どうやったら昇進・昇格できるのか、評価・給与等の仕組みが曖昧でよくわからない
-
09解説
目標や能力像の中身をはっきりさせ、頑張ったら頑張っただけ評価される体系や賃金への反映の仕組みを作成し、提示していくことが必要です。
「頑張ったのに評価や処遇が伴わない」「どうすれば昇格・昇給できるかわからない」と感じさせているということは、社員に「やる気をなくしてくれ」と言っているようなものです。このような会社は、組織風土も「あきらめ」や「やっても無駄」といった沈滞したものになっていることが少なくありません。やったらやっただけの中身としての目標・能力像や評価体系、賃金への反映の仕組みを作り、社員の理解を促していくことが「社員のやる気と成長」を高めていくベースとなります。
-
10
仕事に慣れてきた頃(1年~3年位)に辞めていく社員がいる。人財の定着率低い
-
10解説
社員を育成する体系や人事制度の運営に問題がありそうです。
社員が一人前になるまでの人財育成のステップを体系的に整備する必要があります。「ようやく慣れた頃に退職していく」社員が多くいるような会社には、社員を育成する体系、人事制度の運営が弱いといった傾向がよく見られます。本来、その会社で一人前になるまでに必要なステップや期間があるのに、人手不足を理由に、または育成を十分行わないままに、「勝手に育て」「即戦力」等と都合よく放置していると、状況に対応できなくなったり、見切りを付けた社員は黙って会社を去っていってしまいます。人財定着率は、会社の中長期的な成長を占う先行指標であることを理解することが大切です。